スタッフやコストが限られている中、飲食店の従業員数を決めるのは簡単なことではありません。スタッフが少なければオペレーションが回らず、多すぎれば売上に対してコストがかかってしまいます。
この記事では飲食店の適切な従業員数を計算する方法、シフトを組むポイントについて解説します!飲食店の運営に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
飲食店の従業員数(配置人数)の計算方法
飲食店の従業員数を計算する方法として、次の3種類があります。
- 店舗あたりに必要な人数
- 人時売上高
- FLR比率
店舗あたりに必要な人数は店舗の収容人数を、人時売上高、FLR比率は人件費を考慮した数字です。それぞれの計算式と理想の値を解説しています。
感覚で従業員数を決めるのではなく、データを元に適切な人数を考えましょう。
店舗あたりに必要な人数
飲食店の大きさから必要な従業員数を計算する方法です。店舗の収容人数を式に当てはめて、適正人数を計算します。
ホールスタッフの適正人数は次の式で表されます。
ホールスタッフの適正人数=収容人数÷4(=適切なテーブルの数)÷4
例えば収容人数が30人の飲食店では、30÷4÷4=1.875≒2となり、ホールスタッフの人数は2人程度が適正と考えられます。それに準じてキッチンスタッフ、店舗責任者の人数を決定します。
人時売上高
飲食店の従業員数を決めるには、人件費も計算に入れる必要があります。計算する方法として「人時売上高」と「FLR比率」の2種類があります。人時売上高は従業員による労働時間あたりの売上です。計算式として示すと以下の通りになります。
人時売上高=店舗の月間売上高÷店舗の月間総労働時間(アルバイト、パート含む)
一般的に人時売上高は3,000円~4,000円程度が平均値で、理想は5,000円ほどといわれています。
人時売上高が低すぎると店舗の利益が少なく、逆に高すぎるとスタッフが少ないためお客様に十分なサービスを提供できていない可能性があります。自店舗の数字を計算して、数値が適正内か確認しましょう。
FLR比率
FLRとは、それぞれ
F=Food(食材費)
L=Labor(人件費)
R=Rent(家賃)
を差します。
FRL比率とは、売上のうち食材費、人件費、家賃が占める割合を差します。比率が高いほど売上に対するコストが大きく、利益が低くなります。
FLR比率の計算式は以下の通りです。
FLR比率 = (食材費+人件費+家賃)÷売上×100
一般的にFRL比率は70%以下、家賃を除いたFL比率は60%以下が理想的とされています。比率が高い場合、売上に対してコストが高すぎる可能性があります。
業態別の必要人員目安
カフェは少人数で回せるのに対し、居酒屋やファミリーレストランはホールとキッチンを合わせて一定の人数が必要です。
例えば、カフェと居酒屋、ファミリーレストランなどで比較すると、必要な人数は以下となります。
| カフェ | 居酒屋 | ファミリーレストラン |
|---|---|---|
| 2〜3人 | 4〜6人 | 6〜8人 |
自店舗の客単価や回転率を考慮して調整することが、過不足のないシフトにつながります。
シフトごとの従業員数を決めるポイント
飲食店のシフトを組むにあたり、決めるのは人数だけではありません。配置するスタッフの適性、経験や人件費も考慮する必要があります。
シフトごとの従業員数を決めるポイントは、次の5点です。
- 曜日、時間帯別の混み具合を把握する
- 売上に対する人件費のバランスを考慮する
- シフト管理ツールを利用する
- 従業員の経験、適性に合わせたシフトを組む
- 必要最低限の従業員数で回るよう、オペレーションを見直す
それぞれ詳しく見ていきましょう。
曜日、時間帯別の混み具合を把握する
飲食店には曜日、時間帯によって混み具合が異なります。
例えば居酒屋であれば金曜日、土曜日の夜に客数が増え、オフィス街でランチを提供しているお店なら12時~13時台はお昼休みの会社員で混みあうでしょう。
混雑する曜日や時間帯にスタッフが少ないとお客さんを待たせてしまいますし、空いている時間帯にスタッフが多いとコストが余計にかかってしまいます。
曜日や時間帯ごとの客数や売上を把握し、混雑が予想される時間帯にスタッフの層を厚く配置しましょう。
売上に対する人件費のバランスを考慮する
人時売上高、売上高人件費率で解説したように、売上に対する人件費のバランスも考慮して従業員数を決定しましょう。
飲食店に限らず、経営にあたっては売上高だけでなく利益率が大切です。せっかく売上が伸びていても人件費がそれ以上にかかってしまうと、利益として残る金額は少なくなってしまいます。
毎月の売上や人件費から、コストが適正の範囲内に収まっているか常にチェックしておきましょう。先ほど紹介した人時売上高、FLR比率を使えば人件費が適切な範囲か確認できます。
シフト管理ツールを利用する
シフトを一から自力で入力するのは手間がかかります。シフト作成は非常に大事な業務ですが、時間がかかると他の仕事が回らない場合も。入力を自動化してくれるシフト管理ツールを使って、シフト作成を効率よく進めましょう。
シフト管理ツールの中には、勤怠の管理や人件費の計算をしてくれるものもあります。機械で手間を減らせれば業務量も減り、店舗管理者の労働時間削減も期待できます。
シフト管理ツールを導入するコストより削減できる人件費の方が大きければ、店舗にとっての利益につながるでしょう。ニーズに合わせて最適なシフト管理ツールを選びましょう。
従業員の経験、適性に合わせたシフトを組む
同じ従業員数でも、そのスタッフをどの時間帯に配置するかによってオペレーションの難易度は変わります。人数だけでなく、従業員の経験や適性を考慮してシフトを組みましょう。
経験の浅いスタッフばかりのシフトでは業務をこなすのが難しく、ベテランが中心では逆に人手が余る可能性があります。人数だけそろえるのではなく、従業員の経験、適性にも極端偏りがでないよう注意しましょう。
また、ベテランのみでシフトを組めば業務は楽になりますが、経験の浅いスタッフを教育する機会がありません。ベテランと新人をバランスよく配置し、現在から将来にわたって店舗の業務が滞りなく進むよう工夫する必要があります。
オペレーションを見直し必要最低限の従業員数で回す
飲食店で従業員数を考えるなら、シフトだけでなくオペレーションも見直しが必要です。
余計な業務が多いとその分スタッフの労働時間もかさみ、必要な従業員数も増えてしまいます。従業員数が増えると従業員数が増えてしまい、コストもかさみます。
売上に直結せず優先順位が低い業務はカットするか頻度を減らし、必要最低限の従業員数で営業できるようにオペレーションを見直しましょう。
コストはかかるものの、場合によっては機械による自動化や外注も選択肢に入ります。
飲食店が従業員を確保するための採用方法
店舗に必要な従業員数はわかったものの、現状で従業員数が足りず採用に苦戦している方もいるかもしれません。飲食店が従業員を採用する方法は、主に次の3つです。
- 求人サイトに求人を掲載する
- 自社サイト、オウンドメディアから募集する
- YouTubeやSNSから募集する
自社サイトやオウンドメディア、YouTubeやSNSは集客にも役立つので、採用に限らず運用しておくといいでしょう。
求人サイトに求人を掲載する
最もスタンダードな方法が、求人サイトへの求人広告です。求人サイトは求職者が閲覧するため、効率よく採用活動を進められます。
求人サイトにはさまざまなものがありますが、飲食店に特化した求人サイトがおすすめです。求職者が飲食店の仕事を探しており経験者も多いので、一般的な求人サイトより効率よく人材を探せます。
求人サイトによって掲載料やサポート内容が異なり、中には無料で掲載できるサイトもあります。飲食店の採用におすすめの求人サイトはこちらの記事を参考にしてください。
飲食店に特化していない求人サイトの求職者は、必ずしも飲食店志望とは限りません。求職者と求人がマッチしない可能性があります。
自社サイト、オウンドメディアから募集する
自社サイト、オウンドメディアを持っている場合は、メディア内にスタッフ募集の旨を書いておきましょう。
自社サイトをわざわざ訪問してくれるユーザーは、お店に興味を持ってくれています。募集を出せばモチベーションの高い人材が見てくれるかもしれません。
自社サイト、オウンドメディアはダイレクトにユーザーとコミュニケーションを取る媒体として活用できます。労働条件やどんな人に来てほしいかなど、積極的に発信しましょう。
YouTubeやSNSから募集する
YouTube、SNSアカウントを持っている飲食店は、同じアカウントで採用情報も発信しましょう。
YouTubeやSNSは自社サイトやオウンドメディアより拡散力が高いので、多くのユーザーに見てもらえます。お店のファンで「このお店で働きたい」と思っているユーザーがいれば、投稿を見て応募してくれるかもしれません。
ただし、前提として再生数やフォロワーがある程度いなければ投稿しても人目につきません。顧客獲得のためにも、日頃からYouTube、SNSによる発信はしておくといいでしょう。
リファラル採用(従業員紹介制度)を活用する
既存スタッフからの紹介で新しい従業員を採用する方法は、採用コストを抑えつつ定着率の高い人材を得やすいのが特徴です。紹介者が職場の雰囲気や仕事内容を理解しているため、ミスマッチが少なくなります。
また、従業員自身が友人や知人を紹介するのもよいでしょう。働きやすい環境作りへの意識が高まり、チーム全体の結束力を強める効果も期待できます。
なぜ今、従業員の定着が話題に上がるのか?
コロナ明けの2023年以降、観光需要の回復で飲食店は忙しさを増す一方、人手不足が深刻化しています。採用コストは以前の2〜3倍に膨らみ、「辞めない職場」を作ることが経営の生命線となっています。
- 【最新統計】飲食店は従業員数不足に陥っている
- 飲食店で人手不足が深刻化する理由
順に見ていきましょう。
【最新統計】飲食店は従業員数不足に陥っている
厚生労働省の調査によると、飲食サービス業の従業員は約421万人、店舗数は約61万で1店舗あたりの従業員は約6.9人*。これは日々の営業を回すにはギリギリのラインといえます。
注目したいのが雇用形態の内訳です。一般的な食堂では25.7人中17.4人が非正規、正社員は6.8人にとどまります**。つまり、現場の7割近くを非正規雇用が支えているのです。
この数字が意味するのは、1人でも急に休んだり辞めたりすると、お店が回らなくなってしまう危険性が高いということ。「今日は人が足りない!」という状況が頻繁に起こりやすくなります。
*厚生労働省「飲食店営業(一般食堂) の実態と経営改善の方策」9ページ
**厚生労働省「飲食店営業(一般食堂) の実態と経営改善の方策」23ページ
飲食店で人手不足が深刻化する理由
飲食業界の人手不足には、以下3つの要因があります。
- 労働時間の長さと不定休:ランチとディナーの営業があるお店だと、休憩時間があっても拘束時間は1日12時間を超えることも
- 給料と業務量のミスマッチ:接客・調理・清掃・発注までさまざまな業務をこなしても、時給は他業種とほとんど変わらない
- 教育や評価制度が整っていない:努力しても昇給や将来像が見えず、モチベーションを保てない従業員が少なくない
この構造が、飲食業界全体の「敬遠されやすさ」につながっています。「きつい・給料が安い・将来が不安」というイメージがついてしまっているのです。
人口減少と若年層アルバイトの減少が影響する
少子高齢化が進む中で、飲食店で働く中心層だった学生アルバイトやフリーターの数は減少傾向です。結果、求人を出しても応募が集まらず、時給を上げても効果が薄いケースが増えています。
この状況に対応するには、主婦層やシニア層の活用、外国人労働者の採用といった多様な人材戦略を取り入れることが求められます。
飲食店従業員が辞める理由と“本音”
飲食店の求人に応募が集まらない、入社してもすぐ辞めてしまう…。そのような悩みの背景には、従業員の「本音」があります。表面的な理由だけでなく、より深い部分にある課題を理解することが大切です。
- 飲食店はバイトが少ない?従業員人数の平均
- 「飲食店の正社員は給料高い」はウソ?辞める理由
1つずつ解説します。
飲食店はバイトが少ない?従業員人数の平均
飲食店の人手不足は、配置人数が少ないことに原因があります。
たとえば30席の店舗では、ホール2〜3人、キッチン2〜3人が一般的。これだと、ピークタイムは常にギリギリでアイドルタイムも最少人数で回すため、誰かが休むと一気に負担が増します。
さらにパートやアルバイトなど非正規雇用が多いと、急に休んだり、短期間で辞めてしまうことも。「今日も人が足りない…」「また新人教育…」と従業員のストレスが溜まり、悪循環に陥りやすいことが実情です。
「飲食店の正社員は給料高い」はウソ?辞める理由
厚生労働省の調査によると飲食業の正社員平均月収は約269,500円*。全産業で最も低い水準です。年収は約3,970,000円で、全産業平均(約5,260,000円)より1,290,000円下回ります**。
正社員の離職理由として多いのは、以下のとおりです。
- 月5日以下の休み
- 昇給制度の不透明さ
- 店長でも給与差が小さい
- 評価基準が曖昧
現場では1人が複数業務を担うことも多く、若手の早期離職と定着難に拍車がかかっているのです。
*厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況 産業別」1ページ
**e-Stat「第1表 年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」より算出
e-Stat「1 学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 (産業計・産業別)」
人間関係やシフト不満が離職につながる
給与や待遇に大きな不満がなくても、人間関係のストレスやシフトの融通が利かないことが原因で辞めるケースは多くあります。とくに飲食店はピーク時の忙しさが激しく、スタッフ間の連携不足がトラブルや不公平感を生みがちです。
柔軟なシフト調整と、気軽に相談できる体制を整えることで、離職を防ぎやすくなります。
飲食店業界は給料安すぎ?待遇を読み解く
従業員に長く働いてもらうには、まず今の給料や待遇が世間と比べてどうなのか、客観的に見ることが大切です。ほかのお店や地域の相場と比べて、自店の立ち位置を把握しましょう。
- 飲食店従業員の仕事内容に対する給料実態
- 給料の目安(店舗規模/ポジション別/店長年収あり)
- 給与の決め方と適正水準
順に見ていきましょう。
飲食店従業員の仕事内容に対する給料実態
飲食店従業員は幅広い業務を担いますが、給与は業務量に見合っていない場合もあります。
- ホール:接客、掃除、レジ、在庫確認
- キッチン:調理、仕込み、発注
平均時給は、都会で1,100〜1,300円、地方では900〜1,100円が一般的*。
とくに小規模店舗では「ホールもキッチンも両方できる人」が重宝されます。しかし、給与は片方業務の場合と変わらないケースも。多くの仕事を任せている分、適正な給料を考える必要があります。
*e-Stat「1 短時間労働者の都道府県別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 北海道~群馬」
e-Stat「1 短時間労働者の都道府県別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 埼玉~長野」
給料の目安(店舗規模/ポジション別/店長年収あり)
給与水準は、お店の大きさと担当するポジションで大きく変わります。以下の表を参考に、自分のお店の水準をチェックしてみてください。
| ポジション | 小規模店舗(〜30席) | 中規模店舗(31〜60席) | 大規模店舗(61席〜) |
| アルバイト(ホール) | 時給1,000〜1,200円 | 時給1,100〜1,300円 | 時給1,200〜1,400円 |
| アルバイト(キッチン) | 時給950〜1,150円 | 時給1,050〜1,250円 | 時給1,100〜1,300円 |
| 正社員(一般職) | 月給220,000〜250,000円 | 月給250,000〜280,000円 | 月給270,000〜300,000円 |
| 店長 | 月給280,000〜350,000円 | 月給320,000〜400,000円 | 月給380,000〜450,000円 |
インセンティブ制を導入する店もありますが、基本給が低い場合は離職リスクもあるので要注意です。安定した給料を求める従業員のためにも、基本給の充実を考えてみましょう。
給与の決め方と適正水準
給料を決めるには、次の3つのポイントが大切です。
- 仕事内容に応じた差をつける:責任の重さや任せる範囲に応じて設定する。
- 地域の相場と比べる:周囲の店舗の時給を調べて相場を把握する。
- 生活費を考える:物価や家賃に合わせた現実的な水準に調整する。
また、従業員が納得して働けるように「どうすれば給料が上がるか」という仕組みを明確にしましょう。評価の基準を具体的に示してあげるのが、長く続けてもらうためのカギです。
飲食店の従業員が辞めない職場づくりと効率化
人手不足を解消するには、離職を防ぐと同時に仕事のやり方を効率化することも必要です。従業員にとって働きやすい環境を整えつつ、管理する側の負担も軽くする方法を探りましょう。
- 就業規則・評価制度の導入
- シフト管理・ツール活用の工夫
- チャット導入とAI活用で人員最適化
順に見ていきましょう。
就業規則・評価制度の導入
「なんとなく」で済ませていたルールを就業規則として文字に示すことで、従業員の安心感や信頼感が高まります。とくに飲食業界は働く時間が変則的になりがち。以下の4つのポイントを明確にすると効果的です。
- シフト変更の連絡期限
- 残業や休日出勤時の対応
- 有給休暇の取り方
- 昇給・賞与の基準
評価制度は、「何を基準に評価するのか」を具体的に伝えられる内容にしましょう。接客スキル、仕事の習熟度、チームワーク、売上への貢献度など、項目を決めて定期的に評価します。そうすることで、従業員にとって成長の道筋が見えやすくなります。
シフト管理・ツール活用の工夫
適切な人数で効率よくお店を回すには、次の3つの指標を参考にしましょう。
| 指標 | 概要 | 理想値・目安 |
| ①店舗あたりの必要人数 | 例:収容人数 ÷ 4 ÷ 4 | 30席の店なら約2人(ホール) |
| ②人時売上高 | 売上 ÷ 総労働時間 | 3,000~5,000円が目安 |
| ③FLR比率 | 食材費+人件費+家賃 ÷ 売上 | 70%以下が理想 |
- 人時売上高=1人が1時間で稼ぐ売上額
- FLR比率=経費3要素が売上に占める割合
これらをもとにシフトを設計し、過不足を防ぎます。なお、シフト管理はツールを活用して効率化を進めましょう。次の3つのツールがおすすめです。
| ツール名 | 月額料金(ユーザー単位) | 各ツールの特徴 |
| Airシフト | 無料期間あり3ヶ月目以降330円(税込)※人数課金 | 直感操作シフトボード連携勤怠機能 |
| シフオプ | 300円/ユーザー(1,000名超はIDパックあり) | 自動最適化費用管理欠員可視化 |
| oplus(オプラス) | ①無料(~100人)②100円~③勤怠込200円④自動作成オプション+300円 | 勤怠連携チャット連携複数店舗対応低コスト導入 |
ツールを導入すれば、手作業でのミスやシフト調整の面倒な作業を大幅に減らせます。
チャット導入とAI活用で人員最適化
従業員間の連絡をスムーズにするには、LINE WORKSやSlackなどのチャットツールが便利です。急なシフト変更や業務連絡がスムーズになり、「言った・言わない」のトラブルを減らせます。
また、AIを活用した人員配置の最適化システムも注目されています。過去の売上データや天気、イベント情報などを分析して、必要なスタッフの数を自動で予測してくれるんです。
人手不足や過剰人員を未然に防げますよ。
実際に導入したお店ではシフト作成時間が50%短縮し、人件費を10%削減した店舗も報告されています。初期投資はかかりますが、長い目で見れば大きなコストダウン効果が期待できるでしょう。
教育研修やキャリアステップを用意する
新しいアルバイトに基本業務を丁寧に教える研修制度を整えれば、早期離職を防げます。また、経験を積んだ従業員に責任ある役割や昇給の機会を与えることで、働き続ける動機を強められるでしょう。
キャリアステップが明確な職場は「成長できる環境」として評価されやすく、採用活動でも有利に働きます。
まとめ
従業員数は多すぎるとコストが増え、少なすぎるとオペレーションが回らなくなってしまいます。新しいスタッフを採用したい場合は、求人サイトへの求人掲載やオウンドメディア、YouTube、SNSから募集できます。
求職者に見てもらいやすいのは求人サイトですが、YouTubeやSNSでブランディングを続けていれば「ぜひこのお店で働きたい」と思ってくれる人があらわれるかもしれません。従業員数を決める際は合わせて、日々の業務にムダがないかもチェックしましょう。


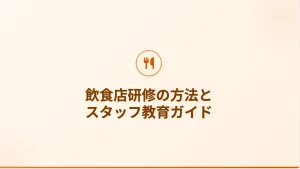
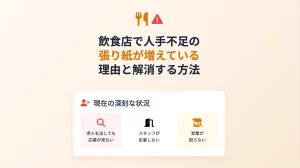
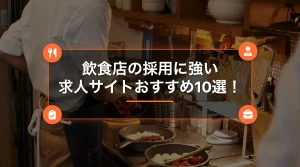
コメント